
道後温泉です。建物が角型灯器よりビンテージ物です(^^;。
海の日は国民の祝日の為日本の国旗が掲揚されています。
お待たせいたしました。広島県と海を挟んでお隣の愛媛県は松山市探訪編をお届けします。
広島から松山までは、瀬戸内海を横断するフェリーで約2時間40分の場所にあります。
距離的には近いのですが、フェリーのため時間はかかります。
今回は仙台の信ちゃん、百円玉くんにも、コメントの執筆をお願いしました。赤字の部分は彼のコメントです。
私のコメントと彼のコメントと、見比べていただいても面白いのではないかと思いますよ(^^)
(一部情報提供 徳田新之助さん・佐川急便 山本さん)
Copyright (C) 1999-2002
信号素材/iida/Hyakuendama
無断での二次利用を堅く禁じます
電車関連信号編
松山はあらゆる電車信号の宝庫です。
路面電車に対しての信号はもちろんのこと、4車線の道路と併走する路面電車と、
さらには、その道路とクロスする鉄道がありの、とにかく電車とは縁の切れない街で(^^;;
私は、道路上で軌道と鉄道が十字にクロスするのを初めて見たわけです(^^;;
そんなこんなで、電車の関連信号はおそらく日本一の数で、これだけを全て見て回るだけで
丸一日はかかるはずです。その数あるバリエーションの中からほんの一握りだけを紹介します。
余談ですが、軌道部分の一部の駅には、電車の存在感知になんと、超音波ドップラ式感知器がありました。
もちろん警察記章付き、プレートには警交仕規付の物で(^^;; 補完できなかったのが悔やまれます(^^;;
| 1 |
  |
| |
|
|
|
|
愛媛県松山市 |
「電車注意」です。ドライバーに注意を促すのが設置目的のようです。
電柱に内照式標識の物と同じセンサーが付いていますので夜間は車が接近すると点灯するようです。
設置場所は、路面電車が車道を外れて住宅街にはいるところ。一種の踏切信号です。
動作はよく観察していないので、不明です。 |
| 2 |
 
    |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H23S |
|
愛媛県松山市 |
| A21S |
路面電車用の信号との併用設置です。このタイプ、広島など路面電車の走っている都市には結構あります。
この信号、「車両用が赤になったら矢印が点灯」ではなく青でも矢印が点灯します。車両用信号とは連動してないようです。
赤い×は電車に対しての赤の現示です。良くあるタイプです。しかし、車両信号との連動はあります。
ここは十字路です。もし車両信号との連動がなければ対向車と電車が衝突してしまいます(^^;;
要するに電車接近感知と車両信号のある一定の現示との条件が重なったとき(論理積)黄色の矢印が出る仕組みです。 |
| 3 |
  |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
|
|
愛媛県松山市 |
松山市内で路面電車の通る部分でよく見る信号です。動作は、消灯か、点灯かのどちらかです。
どの信号も交差点の手前に設置されているようですが、動作の詳細は不明です。 |
| 4 |
   |
| 小糸工業 |
24 |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
1H33P |
|
愛媛県松山市 |
| A31P |
電車用信号です。車両用信号の下に後ろ向きで取り付けられています。
以前普通の車両用矢印のこの設置法を紹介しましたが、あれは車両用の本信号が見えないので違和感を感じますが、
電車用信号であるこちらは車両用とは別動作なのであまり違和感を感じません。
JR松山駅前の物です。車両信号とは一定の条件での関連性があります。
しかし関連の有無は別としてこのタイプの設置、やはり僕は違和感を感じます(^^;; |
| 5 |
車両灯器
 
   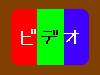
   
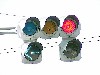   
     |
制御機
  |
| 松下通信工業 |
- |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
VT-171? |
S.?? |
愛媛県松山市 |
| - |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
VT-170? |
S.?? |
| 日本信号 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H23 |
H.7 |
| - |
金属製車両用交通信号灯器 |
ED1083A? |
H.9 |
| - |
電車接近表示板 |
? |
H.? |
| 38 |
プログラム「多段」式交通信号制御機 |
EC9274C |
H.9 |

まずは、上のマップファンウエブのバナーをクリックして場所をご確認下さい。
現場は、国道と車の通りの多い市道?の交差点で、さらに、伊予鉄道がこの交差点に斜めに交わる、複雑な交差点です。
電車通過時は、赤を出しておき、電車が通らない方向に対して矢印で源氏を出します。
また、踏切に当たる部分に対しては、内照式文字板を用いて、注意を促し、赤現示で車を止めるのです。
そのため、複雑な制御となるため、プロ多ユニットに拡張ユニットを増設しているため制御機のサイズもビックサイズです。
矢印だけLEDのタイプです。この手のタイプ、最近広島や仙台でも増殖傾向にあります(^^; LEDは普通の3列タイプです。
踏切と連動する信号です。灯器の下についている赤信号の1灯矢印はきっと赤信号の電球が切れたときに点灯するのでしょう。
「電車接近中」などと表示されるLEDの表示板は日本信号のもので、色々と電車の走行場所によって表示が変わるようです。
制御機ですが、踏み切りと連動する為にかなり制御が複雑なので大きいタイプが使われています。
K形の次に高価な制御機のようです。(iida注/K形より高価だと思われます(笑))
一見リレー式のように見えてしまいますが、小扉の位置で分かります。 |
信号灯器編
信号電材以外のメーカーが各社まんべんなく取り付けられています。
トップシェアは小糸工業だと思います。
市街地を少し離れると、樹脂製灯器も目立ってきます。
市街地で美装化されるポイントではやはり小糸工業が活躍する場面が多いようでした。
| 1 |
   |
| 小糸工業 |
|
金属製車両用交通信号灯器 |
|
|
愛媛県松山市 |
面白い配線方法です。
普通なら上のアームで灯器を支えて、下のアームは途中で途切れてそこから線が出ているのに、
この灯器は下アームも最後まで伸びています。
真ん中から線が出て少し右側に戻っているので別に普通に途中までのアームでもいい気がしますが、
止むに止まれぬ理由でもあったのでしょうか・・・?
そう。百円玉くんの感じているとおり、一目で違和感のある灯器です。
信号素材に足繁く通ってくださるみなさんならば、もうお気づきでしょう。
そう、小糸の灯器に他社のアームを付けているという、変わったパタンなのです(^^;;
解説は百円玉くんの解説通り、下腕が円弧アームタイプで、上腕のみで灯器を支えるタイプですね。
http://www.trafficsignal.jp/~iida/image01/05020016.jpg これが本家のアームですね。
やはりやむにやまれぬ事情があったのでしょう(笑) |
| 2 |
   |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H23D |
H.11 |
愛媛県松山市 |
| 1H33D |
デザイン信号です。まだ設置されて時間が経っていないのでとても綺麗です。
各地域ごとにデザインは色々ですがこの様な直線的なタイプ、個人的に好きです(^^;。
道後温泉からほど近い場所にあるデザイン物です。しかし、お気づきでしょうか、主道路側が250φなのです(^^;;
なぜか従道路側が300φ。面白いですね。
全国的に見ても、このタイプのデザイン物で250φは珍しいと思います。 |
| 3 |

   |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
|
|
愛媛県松山市 |
(上段)このタイプのデザイン信号、同じものが仙台にも設置されています。全国的に分布しているのでしょうか?
(下段)またまたデザイン信号です。この様な信号があると町がきれいに見えていいですね。
このタイプの直線的デザインなので好きです(^^;。
ぶーさんを思い出しながらの撮影です(^^) 上段のものは従道側。下段の物が主道側になりますが、
この交差点、一部分だけ美装化されていなく(^^;;そのギャップが面白かったです。
上段のタイプは百円玉くんのコメントの通り、あちらこちらで見かける、古めのタイプの物です。 |
| 4 |
 |
| 松下通信工業 |
29 |
樹脂製歩行者用交通信号灯器 |
人形 |
|
愛媛県松山市 |
何故かスピーカーが道路ではなく後ろを向いています。渡っている時に聞きにくい気が・・・。
松山のスピーカー設置は、広島のように前方を向いたものと、岡山や山口のように下を向いたものと、
色々なパタンがありました。これは、その、下を向いたもの。
音量は結構大きく、実際に渡ってみましたが聞こえにくさはありませんでした。 |
| 5 |
 |
| 日本信号 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H33 |
|
愛媛県松山市 |
| 30 |
金属製歩行者用交通信号灯器 |
人形 |
|
ぶーさんネタです。
松山市街地は、観光都市らしく、本当に多数のデザイン物が存在します。 |
| 6 |
   
   |
| 信号電材 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H33 |
H.10 |
愛媛県松山市 |
| A31 |
信号電材製のルーバーフード付き灯器です。最近は仙台でも見かけるようになって来ました。
全国的に増加中のようです。
信号電材の視覚制限ルーバー庇ですが、この場所では、視覚制限をしなければならないような理由が見あたりません(^^;;
なぜ設置されたのかその真意が知りたいところですが、後にも先にも信号電材のネタを見たの箱の箇所のみでした。
(信号電材の最新型人形灯器の日本信号版はあちこちにありましたが、こちらも信号電材版は見かけませんでした。) |
| 7 |
     
  |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H33DUN |
H.12 |
愛媛県松山市 |
小糸のLED信号です。デザインアームでとても綺麗です。松山でもLEDは増殖中のようです(^^;
松山で唯一見かけた、LED三位灯は小糸の大粒LED深庇でした。
実はこの小糸の大粒LED、信号素材での掲載は初めてに成ると思います。 |
450φ信号灯器編
愛媛県では大規模な交差点では、450φの信号灯器が使用される傾向があるようです。
(青だけは300φという、全国的にも珍しい灯器が導入されています)
今回確認したのは、京三製作所製と、小糸工業製でしたが、ひょっとすると、日本信号製もあるかも知れません。
| 1 |
      
   |
| 京三製作所 |
24 |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
1H43 |
H.6 |
愛媛県松山市 |
45cmデザイン灯器です。しかも「青だけ30」です。以前ご紹介しました「赤だけ45LED」の逆バージョンです(^^;。
デザインアームに45cm灯器は珍しいです。青より赤・黄の方が大事なのでこの様な信号機になっているのでしょう。
横からのアングルの写真を見ますと、普通の30cm灯器の物と大きさの違いが良く分かると思います。
因みに余談ですが、45cm灯器を支える為、デザインアームの幅がとても広いのですが
裏から見ると灯器よりア-ムの幅のほうが広くて違和感を感じます。
450φが京三樹脂、300φが小糸のアルミ分離タイプ。横からのアングルは大きさの違いがよく解るのではないでしょうか? |
| 2 |
   
    |
| 小糸工業 |
24 |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
1H43F |
H.6 |
愛媛県松山市 |
| A41F |
またまた登場「青だけ30cmの45cm灯器」です。しかも矢印付き。
今回の素材は本・矢印灯ともに小糸製でした。松山は青だけ30cmの灯器しか45cmタイプがないようです。
はい。百円玉くんの云うとおり、愛媛県で採用されている450φ灯器は、全て青だけ300φのようです。
また、型番を見ていただくと解りますが、末尾にFが付いています。
通常小糸の型番で樹脂灯器と言えば1H33Pのようにプラスチック
(ポリカーボネイト) のPが付くのですが、
Fであることから、材質はFRP (fiber glass
reinforced plastics /
繊維強化プラスチック)
でないかと想像できます。 |
| 3 |
    
   |
| 京三製作所 |
24 |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
1H43 |
H.6 |
愛媛県松山市 |
こちらは、茶塗りでない、通常設置の450φです。
でかすぎておもちゃのように見えるのは私だけでしょうか。(^^;; |
| 4 |
 |
| 京三製作所 |
24 |
樹脂製車両用交通信号灯器 |
1H43 |
H.6 |
愛媛県松山市 |
| A31 |
また登場しました。青だけ30灯器です。下には30c
m矢印が設置されています。なんだかオモチャみたいです。 |
弱者信号編
松山市街地は交通弱者に対して優しい信号機が多数設置されており、愛媛県警の意気込みを感じることが出来ました。
同時に、これらの機器を寄贈する地元企業や団体も数多く存在するようで、その土地柄が忍ばれます。
| 1 |
 |
| |
|
|
|
|
愛媛県松山市 |
歩行者に歩車分離信号であることを告げる看板です。この看板を多くの人が見て事故が減ってくれればいいです。
でもココまでしっかり「歩車分離信号です」と歩行者に告げている試験交差点も少ないです。
仙台の交差点などは( http://www.trafficsignal.jp/~hyakuendama/sp.menu.2.htm )
東西方向だけの制御なので結構気づいていない人も多いようです。普通の人は信号機横の表示板なんてあまり見ませんものね・・・。
制御は至ってシンプルで、
1.主道路車両に通行権
2.従道路車両に通行権
3.全方向の歩行者のみに通行権
と言うものでした。信号灯器は従来からの物のようでしたが、制御機だけは新品に取り替えられていましたので、
ひょっとすると、歩車分離信号になったと同時に更新したのかも知れません。
だとすると、結構リッチです。(^^;; |
| 2 |
     
    |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H23S |
|
愛媛県松山市 |
| 30 |
金属製歩行者用交通信号灯器 |
人形 |
|
| ? |
39相当 |
「Ⅱ」形歩行者用押ボタン |
|
|
| 小糸工業 |
62 |
交通弱者用押ボタン箱 |
WS-2-1 |
H.7 |
| 松下通信工業 |
43 |
A形集中制御用交通信号制御機 |
VT-3270A |
S.62 |
| 名古屋電機工業 |
21 |
視覚障害者用交通信号付加装置 |
M-GS-1 |
S.56 |
| 21 |
視障者用スピーカー |
? |
S.56 |
スクランブル交差点にある信号です。この交差点の凄い所は、音響装置を一般企業から寄付されているのです。
以前当サイトでもラジオ大阪寄贈の音響装置を紹介しましたが、それより古い昭和56年製の名古屋電機の物です。
是非こういった活動、もっと広くやってもらいたいものです。
ごもっとも、こういう活動は幅広くやっていただきたい物ですね。
さて、この交差点の最大の特徴は、何と、スクランブル動作時に、ピヨピヨとカッコーが同時に鳴きます(^^;;(^^;;(^^;;
こんなの初めてですよ(^^;; すごいです。しかも大音量で。
他にも、名古屋電機のスピーカーが中四国地方で珍しいほかに、弱者ボタンがあったりデザイン柱埋め込みの2形ボタンがあったりと、
めずらし物だらけの交差点でした。
警交仕規の217号の音響付加装置では、このように同時にピヨピヨとカッコーが鳴ること自体が禁止されているそうで、
21号の付加装置ならでわと云った技です。 |
| 3 |
     
     |
| 小糸工業 |
23 |
金属製車両用交通信号灯器 |
1H33D |
|
愛媛県松山市 |
| 30 |
金属製歩行者用交通信号灯器 |
人形 |
|
| 京三製作所 |
|
横断予告表示灯 |
CA1-1LS |
S.62 |
| |
横断予告制御装置 |
CAC-13A |
S.62 |
| 名古屋電機工業 |
21 |
視覚障害者用交通信号付加装置 |
N-GS-1 |
S.64 |
砂時計タイプの前の横断予告灯です。待ち時間がストップウォッチの様に減っていきます。
しかも音響装置が名古屋電機でスピーカーが旧型です。こちらの横断予告灯も寄贈品のようで、
松山は本当にすごい街だと思います。
そのようです。愛媛県は交通弱者機器等に関してのスポンサーが沢山いる土地柄のようです。実に良いことです。
この待時間表示器は、待ち時間の秒数が減っていく物ではなく、待ち時間を10分割して、その答えを数字で表すタイプで、
砂時計形待時間表示器をデジタル表示にしたようなものでした。
また、音響装置ですが非常にレアな「昭和64年3月製造」です。 |
交通機器編
特に超音波感知器のバリエーションが多く、警交仕規6号の超音波感知器や警交仕規27号のバス感知器などの
古い、レア感知器も、普通のようにあちらこちらに設置されているのが目に付きました。
美装化地区では、これらの制御機は自立式になる傾向が強いようで、あの小さい箱のC形感知器の箱でさえ
自立式に成っており、これも全国的に見て珍しい傾向と感じました。
| 1 |
   |
| 松下通信工業 |
6 |
超音波式車両感知器 |
|
S.50 |
愛媛県松山市 |
松下通工製の旧世代車両感知器です。最近めっきり見かけなくなりました。
このタイプだと制御機からパチパチという音がするのですが、この感知器の制御機に耳を当ててみると・・・
残念ながら音はしませんでした(T0T)。しかしながら存在が貴重になっている現在に更新されずに頑張っているのがうれしいです。
音がするのはヘッドからですね(^^;;
このツボ形タイプはパチパチ音の聞こえないタイプですが、それにしても、警交6号の感知器が市内の至る所に残っていました。 |
| 2 |
    |
| 日本信号 |
204版1 |
C「分離」形超音波式車両感知器 |
EA3161A |
2000 |
愛媛県松山市 |
C分離型車両感知器です。普通は感知器のヘッドが設置されている柱と同じ柱に制御機が設置されるのですが
この感知器の場合、本当に「分離」して制御機は別な場所にポツンと自立柱タイプで設置されていました。
この感知器は、地点感応の制御用ではなく、渋滞を感知するための集中制御用の感知器なのですが
私が今まで見てきた他県での運用からは想像できないことが一つあります。
それは、管制センターのメーカー(愛媛県は松下)と、メーカーが合っておらず、メーカーが日本信号であると言うことです。
このほかにも京三のセンサー有りの、小糸のセンサー有りの、色々でした。
超音波感知器のバリエーションが非常に多い、と言うことが出来そうです。 |
| 3 |
     |
| 東芝 |
220版1 |
小型情報板 |
E31834A |
1997 |
愛媛県松山市 |
東芝の小字表示板です。こちらもC分離型と同じく接続箱が独立して離れたところに設置されています。
松山は自立制御機が好きなのでしょうか?(^^;
警交仕規220号の小型文字版ですが、警交仕規の付いた表示板としては珍しく、なんと、東芝の製品です。
東芝と言えば、今まで、光学式車両感知器しか確認していませんでしたので新たなる発見が出来ました。
これからの動向が気になるところです。 |
| 4 |
  |
| 松下通信工業 |
206版1 |
光学式車両感知器 |
VT-2723 |
2000 |
愛媛県松山市 |
普通の光学式車両感知器です。
ごくごくふつうのものです(^^;; |
| 5 |
  |
| 松下通信工業 |
204版1 |
C「分離」形超音波式車両感知器 |
VT1910C? |
H.7 |
愛媛県松山市 |
| 臨時仕様制定時の物もありました。 |
| 6 |
   |
| 松下通信工業 |
6 |
超音波式車両感知器 |
|
S.50 |
愛媛県松山市 |
またまた登場しました旧世代車両感知器です。
松山の偉いところは、この様な古い交通機器も色を塗り替え使い続けているということです。
この素材は前出の素材と違い、デザイン柱についていますので多少違和感を感じます。
それにしても、使えるものは最後まで使うという良い心がけだと思います。
全くその通り。我が広島にも見習って欲しい部分であります。 |
| 7 |
    |
| 松下通信工業 |
27 |
路側式バス感知器 |
|
S.53 |
愛媛県松山市 |
こちらも、旧世代のバス感知器です。
広島では、バス感知器に限れば、旧世代の感知器も結構残っています。
しかし、見ての通りデザイン柱に設置された物でして、昔からあった物を色を塗り替えてデザイン化したものであろうと思います。
こういったケースの場合広島では間違いなく新品に変わってしまいます(^^;; |
| 8 |
  |
| 日本電信電話 |
|
駐車場案内システム |
個別案内板 |
H.6 |
愛媛県松山市 |
先ずは、表示板をご覧ください。何の変哲もない普通の駐車場案内板です。
しかし!プレートを見ると「日本電信電話株式会社」となっているではありませんか!!NTTですよ(^^;
電話の会社が交通機器を作っているなんて知りませんでした。大変貴重な素材です。
そう。普通なら信号素材では扱わない素材なのですが製造メーカーがなんとNTTだったために撮影しました。 |
| 9 |
   |
| 小糸工業 |
66 |
専用パタン式表示板 |
KCS-M-1 |
H.5 |
愛媛県松山市 |
決まったパタンの看板に時間のみを表示するタイプです。
(M)部分が括弧書きになっているので、他のタイプもあるのかもしれません。
はい、他のタイプも存在しますよ(^^)
専用パタン板なので、この場合の専用とは、時間を表示する数字のフォントを指します。 |
Copyright (C) 1999-2002
信号素材/iida/Hyakuendama
無断での二次利用を堅く禁じます







































