<大阪府> 4方向1灯点滅
| 1方向だけずれた4方向1灯点滅 |



 
|
 撮影 大阪府摂津市 掲載 2002/3/1 差替追加 2008/1/23 撮影 大阪府摂津市 掲載 2002/3/1 差替追加 2008/1/23
|
|
|
| 2方向だけずれた4方向1灯点滅 |


 


|
 撮影 大阪市住吉区 掲載 2005/7/9 撮影 大阪市住吉区 掲載 2005/7/9
|
|
|
| 背面上部を吊られた4方向1灯点滅 |




|
 撮影 大阪府泉南市 掲載 2004/10/21 撮影 大阪府泉南市 掲載 2004/10/21
|
|
|
| 4方向別々なのに銘板が1枚 |

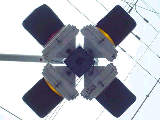
|
 撮影 大阪市北区 掲載 2002/8/28 撮影 大阪市北区 掲載 2002/8/28
|
|
|
| 1方向だけずれた4方向1灯点滅 |



 
|
 撮影 大阪府摂津市 掲載 2002/3/1 差替追加 2008/1/23 撮影 大阪府摂津市 掲載 2002/3/1 差替追加 2008/1/23
|
|
|
| 2方向だけずれた4方向1灯点滅 |


 


|
 撮影 大阪市住吉区 掲載 2005/7/9 撮影 大阪市住吉区 掲載 2005/7/9
|
|
|
| 背面上部を吊られた4方向1灯点滅 |




|
 撮影 大阪府泉南市 掲載 2004/10/21 撮影 大阪府泉南市 掲載 2004/10/21
|
|
|
| 4方向別々なのに銘板が1枚 |

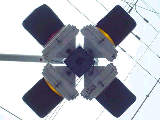
|
 撮影 大阪市北区 掲載 2002/8/28 撮影 大阪市北区 掲載 2002/8/28
|
|
|